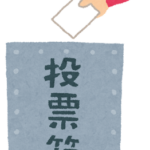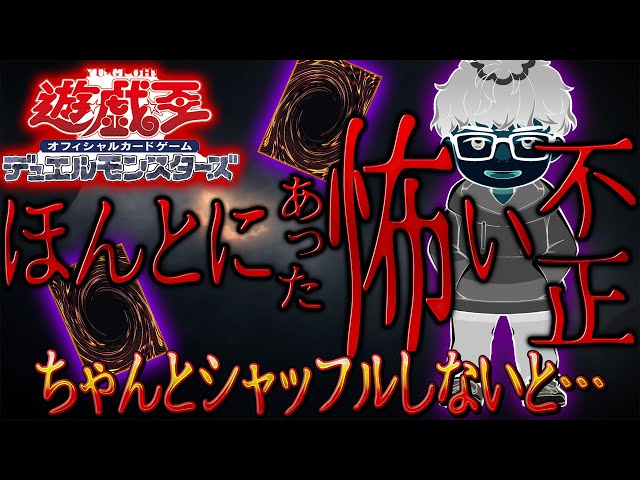
自分が見た中で「これは面白い!」と感じた動画(YouTubeでもニコニコでも)を紹介するコーナーです。今回は「【遊戯王】昔やられた『恐ろしい不正』を語る世界4位【シーアーチャー切り抜き/遊戯王/マスターデュエル】
」です。
日常に潜むパンドラ
こちらはYoutuberのシーアーチャーさんの配信切り抜き動画です。遊戯王の競技勢として長年プレイされているシーアーチャーさんが、紙での対戦で相手にやられたことがある不正行為について話しています。
カードゲームの対戦直前は、デッキのカードを混ぜる「シャッフル」を行います。自分で自分のデッキをシャッフルするだけだと不正し放題になってしまうので、基本的に大会や知らない人との対戦などちゃんとしなければいけない試合ではお互いのデッキをシャッフルするのが常です(自分は友達同士の対戦だと省いちゃうタイプでしたけどね)。
しかし、お互いにシャッフルをしたら不正が無いかと言ったらそんなことは無く、相手のデッキを触れている時にイカサマをするプレイヤーも居ます。今回の動画では、シーアーチャーさんが注意喚起として自分もやられたことがある技を紹介しています。
紙のカード特有の現象として、「手触りでカードのレアリティが分かってしまう」というものがあります。普通、カードは傷まないようスリーブ(プロテクター)に何重にも入れられていて、触ってみてもカード毎の違いなんて分からないように思えますが、カードを弾くように叩くと硬さでノーマルカードか加工されたレアカードか分かっちゃうんですね。
これを利用して、レアカードをデッキのトップに固める or 下に固めるようにシャッフルすることで、相手の初手を操作してしまうと。カードのシャッフル方法として、一般的にイメージされるヒンズーシャッフル、デッキを2分割して重ねるファローシャッフル、1枚ずつ並べていくディールシャッフルの3種類が主な手法としてあって、ディールシャッフルの時にパチンパチンと弾くようにシャッフルしてくる人は、「ヤッてる」可能性が高いと。
お次はファローシャッフルの時の手口で、ファローシャッフルでデッキを二分割している時に、片方をちょっと持ち上げてチラッと下のカードを見る方法。ファローシャッフルの性質として、二分割を繰り返す都合上、元のデッキの最上部のカードは上部に、元の最下部のカードは下部に残りやすくなります。
そのため、ファローシャッフルだけだとしっかりカードが混ざりきらないのでファローシャッフルの後に別のシャッフルを入れるんですが、ファローシャッフルで下のカードをチラ見して下に弱いカードが固まっているのを確認した後で、ヒンズーシャッフルでサッと下のカードを上に持ってきて、積み込み完了と。
真似をせず、咎める側に
今回の動画では上記の2つの方法が暴かれていましたが、他にもイカサマの仕方は色々あるでしょう。カードを使ったアレコレなんてマジックの定番ですからね、磨いた技を悪いことに使おうとする野生のパンドラたちがそこいらに潜んでいても不思議ではありません。
ただ、動画で一緒に語られていたのは、この手の不正は今では殆ど見なくなったとのことです。そういう手口が周知されていき、プレイヤーもジャッジも見る目が厳しくなっていき、新しい技の開発なんかもしようが無い(原始的なカードテクニックなんてもう研究され尽くしてる)でしょうから、サマ師が暴れる余地はどんどん無くなっているんでしょう。
と言っても、セコい奴はどこにでも居るので、こういう技があると知っておくことは自衛に役立ちますし、自分がプレイする時も疑われるようなプレイを避けることで無用なトラブルの芽を事前に摘むこともできます。身内同士の対戦ならまだしも、知らない人と対戦する時はこんなことがあるかもしれないと頭の片隅に置いておくのは大切です。
自分はもうマスターデュエルで遊戯王に復帰して以降、デジタルの快適さを知ってしまって完全にデジタルでしかカードゲームをやっていないんですが、こういう不正を一切考慮しなくていいのもデジタルの良さですね。紙には紙にしかない魅力が沢山ありますが、あらゆる煩わしさから解放されたい人はデジタルの方が向いてるんでしょうね。紙のカードの感触も恋しいけどね。
(Twitterでたまに遊戯王について呟いているのでフォローしてね→@yolda2s)
(この記事が面白いと思ったらSNSでシェアや感想の投稿などよろしくお願いします!)
関連コンテンツ






 「麻乃ヨルダ」と申します。カードゲームオタクです。連絡やメッセージはツイッター(
「麻乃ヨルダ」と申します。カードゲームオタクです。連絡やメッセージはツイッター(